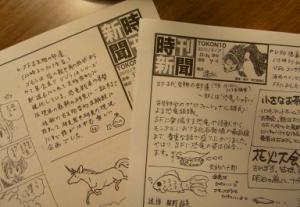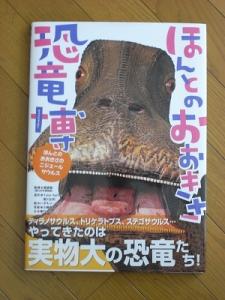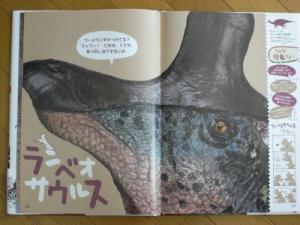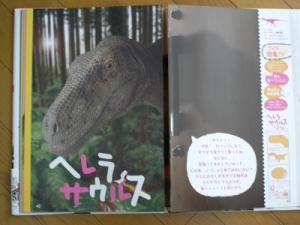パンチョさんfromアルゼンチン
2010年8月19日 / 恐竜・古生物
18日
アルゼンチンから研究で日本に来られている古生物学者・パンチョさんこと
Francisco Juan Prevosti氏と京都で合流。
折角だし、いかにも京都!な所で昼食。
画像手前がパンチョさん。奥は、パンチョさんと同じ食肉類が専門の
荻野慎太郎さん。
出された料理の中の一品。パンチョさん、苦手な食べ物無し。
仲居さんから「おーきに」というお礼の言葉を伝授されたり。
食事中は、私の作品のファイルを見てもらったり、アルゼンチンの古生物の話を伺ったり。日本の子供達の間ではギガノトサウルスとかカルノタウルス等アルゼンチン産の肉食恐竜が結構人気あるよ、と話すとちょっと驚いてました。
昼食の後は、京都大学総合博物館へ標本の調査。
パンチョさんがお仕事中、こちらは荻野さんや、その他京大の学生さんとおしゃべり。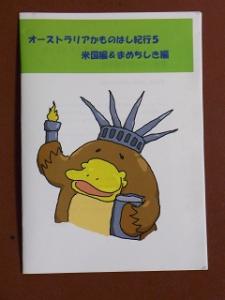
その際に、とある学生さんから頂いた冊子。
同人誌としてイベントで販売もされているそう。
サイトもあります>こちらカモノハシ好きに悪い人いないんだろうな、と思わせる、ほんわかした雰囲気ながら、要所要所には「さすが研究者!」という本格的な部分も。同人誌でありながら、動物研究の実際を楽しく知る事が出来る、なかなか素敵な本です。著者の学生さんとは台湾国立自然科学博物館のカモノハシ展示の話で盛り上がったり。
パンチョさんの調査終了後は、近くの居酒屋で飲み会。
パンチョさん、日本の歴史が相当詳しい。「モンゴルが日本に攻めて来たときにですね~」と切り出すと「2回来たんだよね」と合いの手。他にも「平家物語」「古事記」なんかも知ってるし。
居酒屋で店員を呼ぶときの、男性の「すいません!」と女性の「すいませ~ん!」の音の伸びの違いが気になる、という指摘が面白い、というか流石研究者? で、その後自ら「すいませ~ん!」と日本語で店員さんを呼んでしまう実行力も流石古生物学者、、、かな?
アルゼンチンを含む南米の研究者や恐竜関係者とは、シンポジウムや学会、ネットでは少し交流もあったりしますが、今回ほどいろいろとお話が出来たのは初めて。パンチョさんのお人柄もあり、楽しい1日になりました。
アルゼンチンは恐竜だけでなく、化石哺乳類も有名な物ばかりですから、一度は行ってみたいですね。