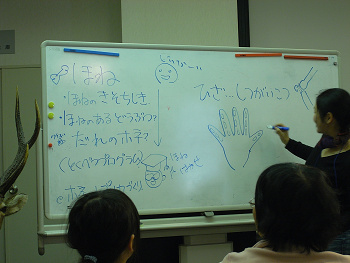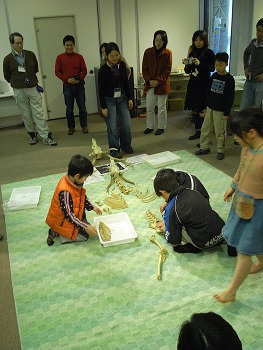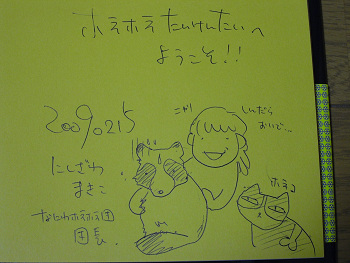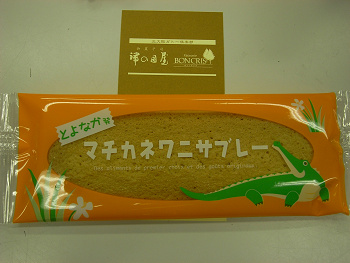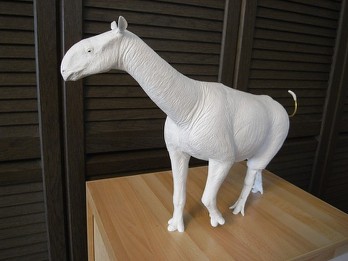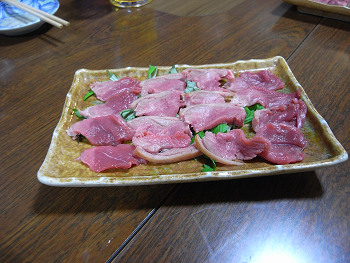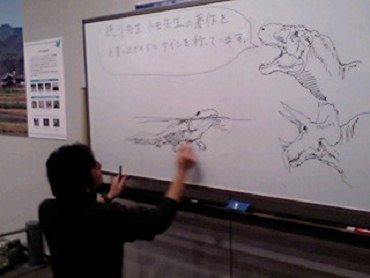インドリコ&マラウィ
2009年2月20日 / 造形・イラスト作品
インドリコテリウム、塗装前です。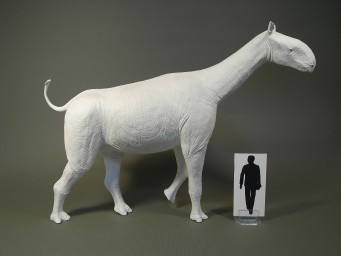
耳はもう少し小さくても良かったかな?
こちらは少し前に完成したマラウィサウルスです。
背中のトゲは、ティタノサウルス類という事で付けて
みましたが、全くの想像です。
マラウィは、ラペトサウルスと並んで比較的保存状態の
良い化石が発見されているティタノサウルス類という事で、
丹波竜の復元を考える際には外せない恐竜。
といっても、現段階では丹波竜はティタノサウルス形類ではないかと
考えられているので、復元の可能性の幅はもっと広い事になります。
ティタノサウルス形類だと、ブラキオサウルスも入っちゃいますからね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
現在イチ押しアニメ、、、、他をほとんど知らんのですが。
一度に全部観ちゃうと勿体ないので、ちょっとずつ観てます。
今、皇帝ペンギン2号のところ。