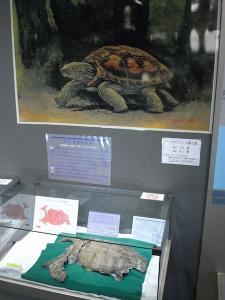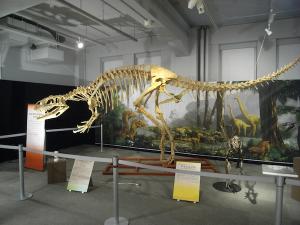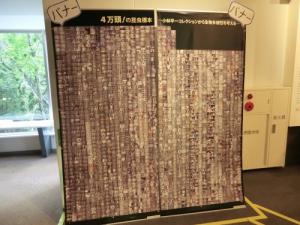葛生化石館・企画展「単弓類ってしってる?」
2014年7月23日 / 博物館・特別展見学
●葛生化石館で開催中の
企画展・「単弓類ってしってる?」に
私の作品が展示されています。
展示の様子を化石館の学芸員さんが送って下さったので紹介。
イノストランケビア。
これは葛生化石館の常設展示。
国内では恐らく唯一の常設展示。
私は海外でも見た事が無かったりします。
企画展展示のディメトロドン。
個人的にはこれが目玉の
コティロリンクス全身骨格レリーフ。
アメリカ自然史博物館で展示されているもののレプリカ。
そして、横の模型&頭骨レプリカは私の作品&所蔵品。
頭骨はオクラホマ・サムノーブル自然史博物館収蔵のものの
レプリカ。この3点が並ぶ光景が見られるとは!
というか、まさか自分のコティロリンクスが
全身骨格展示と同じ舞台に立つ日が来るとは、、、、。
8月3日(日)には関連講演会
単弓類:恐竜以前に栄えた動物たち」 も開催。
講師は平山廉先生。時間は14:00から(約1時間)。
単弓類を題材にした企画展、そして講演会は
なかなかあるものではありません。
単弓類好きは是非葛生へ!
単弓類を含むペルム紀の古生物に興味のある方には
オススメです。


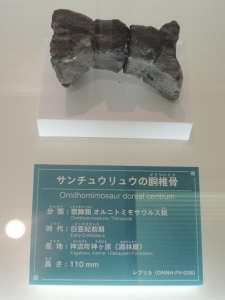
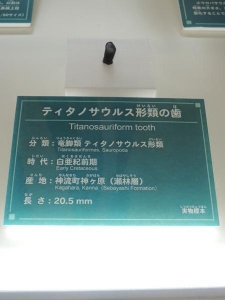


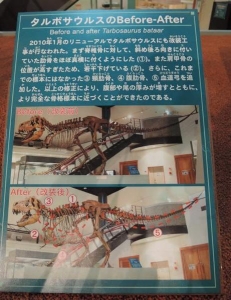





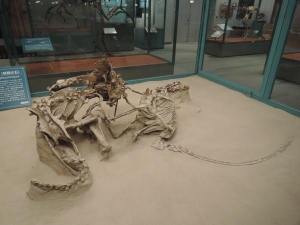
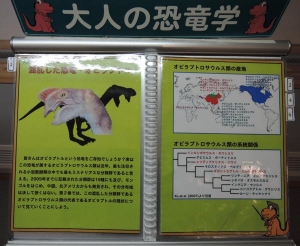

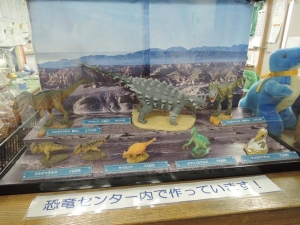
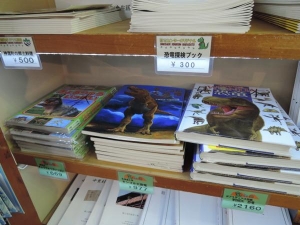







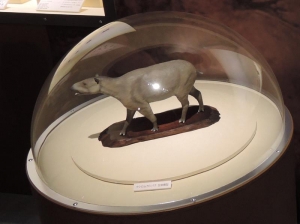











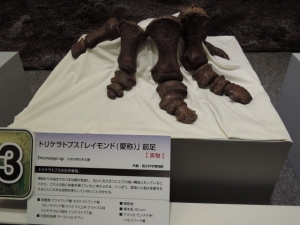
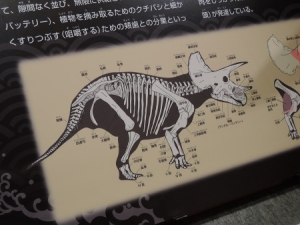
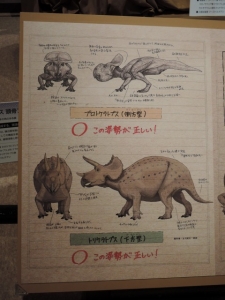









![1240227_586956138012884_461434434_n[1]](https://afragi.xsrv.jp/weblog/wp-content/uploads/img/20130920214708abas.jpg)
![578944_586956171346214_1364038830_n[1]](https://afragi.xsrv.jp/weblog/wp-content/uploads/img/20130920214711da6s.jpg)
![1236960_586956198012878_1720615369_n[1]](https://afragi.xsrv.jp/weblog/wp-content/uploads/img/20130920214709591s.jpg)







s.jpg)