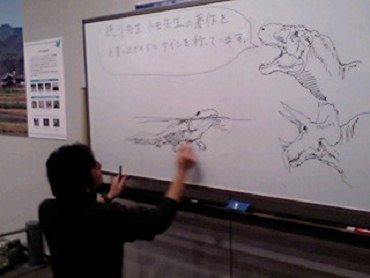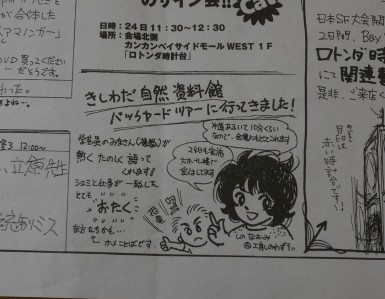恐竜粘土造形教室at六本木ヒルズ(+α)
2010年8月3日 / イベント・教室・講演
7/31、8/1の2日間、
六本木ヒルズにて開催の「世界最古の恐竜展」に合わせ
企画されたイベントの一つとして、恐竜粘土造形教室が行われ、
その講師を担当しました。
今回は、市販のキットを使った、
プラスチック製の恐竜骨格に紙粘土で肉付けをするという内容
私が講師をする時にはお馴染みの最初の掴み。
作業の前に骨格の見方を勉強して貰っています。
模型製作を通じて骨格の事を学んで貰うのが、今回の教室の目的。
作業はカメラで撮影、大きなモニターで皆さんにも見て貰える様に
していましたが、難しい所は子供達に実際に手元を見て貰いました。
私が教室の講師をする際、会場の施設に古生物、地質の
専門家・学芸員等が居られない場合は、古生物を
研究・勉強されている学生さんに出来るだけ
お手伝いに来て頂くようにしています。
参加者の質問には、専門家では無い私では
ちゃんと説明出来ない物も多いですし、
古生物学に興味のある子供達に、実際に研究している人と
話しが出来る機会を作れれば、と思っているからです。
今回は東京大学総合研究博物館・河部さんにお願いしました。
河部さんとのコンビでの教室は初めてなのですが、
専門的な内容でも、非常にわかり易く解説され、
またそのお人柄もあってか、教室中、また教室終了後も
質問する方が多数。私よりも人気があったような(笑)。
教室終了後、記念撮影。背景がまさに六本木ヒルズが
会場なのを表しています。
教室終了後は、河部さんの提案で2人で恐竜展会場へ。
教室参加者と会うと、またそこでいろいろお話ししたり、
展示物の解説をしたり。これも楽しかったです。
また、去年の丸善での作品展に来てくださった子供さんとの再会も。
顔見知りの参加者が居られると、こちらもちょっと心強いものです。
今回の教室、私がまだ不慣れな部分もあるので、
段取り等でミスしそうな所もあったのですが、
河部さんとスタッフの方の機転&好フォローで
事なきを得る事も何度か。
2日間で4回の教室開催でしたが、回数を重ねる毎に
チームワークも良くなってくるので、この2日間で
終わってしまうのが勿体無い。
参加の皆さんの集中力や理解力の高さにも助けられ、
私も楽しい時間が過ごせた2日間でした。
8/2
午前中は、日本橋三越の恐竜展。
小規模ながら、なかなか興味深い&質の高い標本の展示が
あったのですがほとんどが撮影不可なのが残念。
撮影可展示から。

これはこれで味わい深い、、、、。
次は、進化学会・公開シンポジウム聴講のため
東京工業大学へ。

校門入って直ぐの建物に展示中のシーラカンス。
このシーラカンスについてはこちら。
シンポジウムは、平山廉先生の恐竜に関する講演が
目的だったのですが、他の3つの講演も面白かった!
日頃、あまり接する機会の無い分野の話を
聞ける良い機会になりました。
講演終了後も、会場に来られていた真鍋真先生に
六本木ヒルズでの教室の報告が出来たり、
その他、知り合いにも何人も会えたり。
今度の魚大会用の造形をする上で核となりそうな
情報も仕入れられたし、「ちょっと、ついでに~」
と気軽に行ったにも関わらず、収穫の多い日でした。
.jpg)