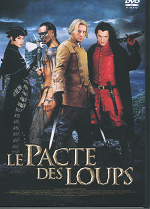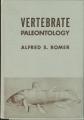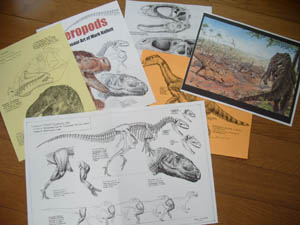アシスタント 1日目
2007年1月7日 / その他
以前にも紹介した、荒木一成さんの
恐竜模型教室のお手伝いを2日間する
事になり、今日はその1日目。
全くの素人さん、しかも親子連れの参加者に
どういう内容で造形を教えるのかと
興味と心配が半分ずつでしたが、
そこは流石は経験豊富な荒木さん。
無駄無く、無理無く、それでいて中身の濃い
内容で、2時間の教室にも関わらず塗装まで
辿り着く参加者も。
アシスタントの私やSHINZENさんも、
その段取りに乗ってしまえば良いので、
意外にアドリブも少なくて済んだり。
また、お子さんの手伝いをする内に、だんだん
眼が真剣になってくる親御さんが微笑ましく、カッコイイ。
という事で、初日の様子は荒木さんのブログを。
今夜は会場近くのホテル泊。
昼食時、私がソフトクリームを食べようとして
時間の都合で泣く泣く諦めた事を覚えていたSHINZENさん、
ホテル到着後「近所にミニストップがあったんで、
ソフトクリーム食べに行きましょう!」と誘いに。
良い奴やなぁ、アンタ。
そんなSHINZENさん、今、隣の部屋でワンフェス用の新作
造ってるらしいです。頑張れ~!壁越しに応援してるぞ~。