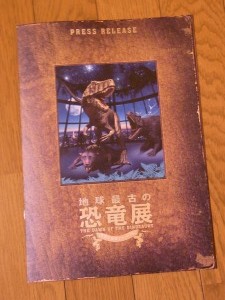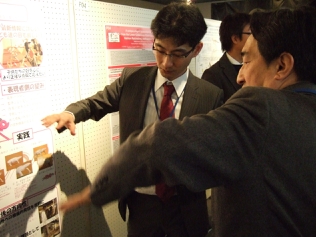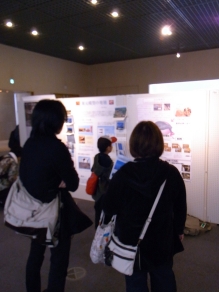只今、台湾 その2
2010年3月6日 / 2010年 台湾
5日
午前8時30分に、ホテル前にでSuchusさん夫妻と
合流。お二人と直接会うのは初めて。
知り合った経緯は、また後日。
とりあえず、奥さんは驚くほど完璧に日本語が、
Suchusさんもかなり英語が話せる事が分り、
言葉の心配の必要は無しに。
最初の見学先は「世界恐龍大展」
内容は、日本の林原自然科学博物館による「恐竜ラボ」
とほぼ一緒。
昼食。

お粥には砂糖を入れるののもアリ。
違和感なく美味しい。
午後は1月末に開館したばかりの国立台湾博物館・
土銀展館の古生物展示へ。
タルボ、ファンヘティタン、
チョンユアンサウルス等の全身骨格が。
チョンユアンサウルスは、漢字表記だと
洛陽中原龍。中国史好きを熱くさせる学名です。



見学者用ロッカー。
ドアの一つ一つに植物をあしらってあります。
素晴らしい出来の、三葉虫脱皮連続模型。
夕方は私の希望で、台北の模型店&トイショップめぐり。
小規模のお店が集まった中野ブロードウェイの
ような場所に案内して貰いました。
そのビルの地下で夕食。
この日は、Suchusさん宅に泊めて頂く事に。
玄関のプレート。
一晩、この方と一緒でした。
続く。
>「世界の恐竜博物館見聞記」ホームへ