アクロカントサウルス製作 その6
2011年1月19日 / 造形・イラスト作品
アクロカントサウルス、塗装前状態。

特に完成を急ぐ場合は別ですが、造形が終了したら塗装まで1週間ほど時間を置く事にしています。その間に傷やヒビ、ディテールの抜けを見つければ修正し、またどんな色に塗るかもいろいろと検討します。ちょっとした熟成期間のようなもんでしょうか?
アクロカント製作、前回の記事はこちら。
2011年1月19日 / 造形・イラスト作品
アクロカントサウルス、塗装前状態。

特に完成を急ぐ場合は別ですが、造形が終了したら塗装まで1週間ほど時間を置く事にしています。その間に傷やヒビ、ディテールの抜けを見つければ修正し、またどんな色に塗るかもいろいろと検討します。ちょっとした熟成期間のようなもんでしょうか?
アクロカント製作、前回の記事はこちら。
2011年1月16日 / 日本古生物学会
1月14日
京都大学で古生物関係の発表が別枠で2つ。
それぞれ案内を頂いたり、知り合いの研究者さんに
誘って頂いたりで参加する事に。
その内の一つ。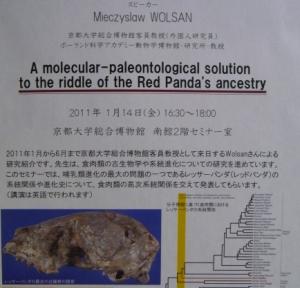
レッサーパンダってRed Pandaとも呼ばれる、
というか英名としてはこっちのほうが多用されているようです。
なんか強そうだ。
”「レッドパンダ2010」主演 ドルフ・ラングレン”的な。
ちなみに発表は英語。聞き取り易い丁寧な英語でしたが、
もちろん私の英語力では内容を理解出来る訳ではありません。
そもそも日本語の発表でも私には難しい内容だったような(笑)。
それでも、ほんの少し分る部分だけでも勉強になります。
その後は懇親会。
Wolsanさんにポーランドの古生物アーティストの
お話を短い時間ですが伺えたのが良かったです。SVPでも東欧の古生物アーティストにはまず会えませんしね。
2011年1月13日 / イベント・教室・講演
1月9日の「第3回モササウルス研究会」に講師の一人として
参加しました。
もう一人の講師・渡辺さんによる解説中。
私の担当部分は今まで2回とは少し内容を変更。
初めてのネタで不安だったのですが、結構参加者の反応も良く、
悩みながらも作業を楽しんで下さったよう。
今回は、岐阜県・瑞浪市化石館の学芸員さん「他」も
来場されました。ブログにも、その際の様子や、
翌日の化石採集会のレポートがあります。
という事で、今、瑞浪と言えば!

資料館の駐車場&化石採集会でも注目を浴びていたようです
(そりゃそうだ)。
瑞浪Mioちゃんについてはコチラも。
2011年1月8日 / その他
「The Artist & The Scientists」
オーストラリアのアーティストと2人の古生物学者が共同で関わった仕事を、それぞれの立場の見解も含めて紹介しています、、、、と思うんですが、何せ英語なんで「って感じかな~」な理解です。各仕事の項が研究者サイドとアーティストサイドの2つに分けられた構成になっています。
アーティストのPeter Trusler氏は
「Magnificent Mihirungs」や「Wildlife of Gondwana」の表紙を含むイラスト等、オーストラリアの古生物本ではお馴染みと言って良い人。今回紹介の本は氏の画集という面もあり、見るだけでも十分楽しめます。
で、そのTrusler氏のイラストを使った切手が発行されていまして、それは随分前に入手していたのですが、これがまたなかなか凝ったもので。小冊子(といっても、しっかりした作り)状態で、切手に採用されているイラストも別枠で大きく紹介されており、なおかつ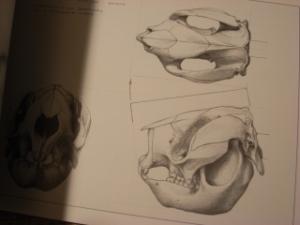
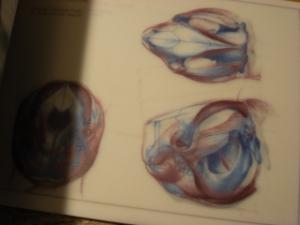
と、骨格から始まり、その上に下の透ける紙に印刷された筋肉図、生体図が重なっていくページも(画像は2枚だけ。全部見たい方は、是非その切手か、同じイラストが掲載されている「The Artist & The Scientists」を)。先にあげたオーストラリアの古生物本もどちらも非常に良い内容ですし、良い作品が良い本(造本も含めて)に使われている、見ていて嬉しくなる仕事の数々です。
・・・・・
6日は、きしわだ自然資料館特別展「モササウルス」会場にて、古生物の話題を通じてツイッターでやり取りをするようになったお二人とプチオフ会。普段、ほとんど関わる事が無い分野のお話をいろいろと伺えた上に、それが自分にとって参考になる話題も多く楽しい集まりになりました。
2011年1月1日 / その他

・・・・・
今年のネタはケラトガウルス(Ceratogaulus)、、、
というかエピガウルス(Epigaulus)のほうが通りが良いかも。
今はエピガウルスはケラトガウルスとして
扱われているようです。系統としては齧歯類、現生では
ヤマビーバーが比較的近縁種(かな?)、
とにかくウサギネタとしてはかなりのお題違いです。
と言って、次の子年はまだまだ先ですし、
化石種のウサギ類ネタで良いのが無かったので、
ウサギっぽい雰囲気の古生物という事でコレにしました。
とは言え、今回は雰囲気先行&デフォルメデザインの
造形なので、正確性は全くないです。
色も正月&ウサギっぽく、って事で白です。
材料はカラースカルピー。
スカルピーの色をそのまま使っているので、
塗装は一切していません。
国立科学博物館のエピガウルス全身骨格。
もう一度、しっかりと造ってみたいです。
・・・・・・
ではでは、今年も宜しくお願い致します!
(大晦日・元旦の記事にコメント欄が無いのは毎年恒例ですので)
2010年12月31日 / その他
23日の「モササウルス展」ギャラリートークの後は、
忘年会に2つほど出た以外は、ほぼ外出無しでした。
年末年始の時間がある内に、いろいろ作業を進めたい、
来年に向けて下準備を出来るだけしてしまいたいと
欲張りすぎた感が。先ほど、やっと一息つけた所です。
という事で、来年に向けての景気づけに。
「全力全開イイ湯加減 全力全身ぬるま湯加減♪」
良い歌詞です!
今年もあと残すところ僅か。
皆さん、良いお年を~。
2010年12月28日 / その他
●来年1月28~30日開催の日本古生物学会例会の
プログラムが発表になりました。
29日には今年冬の学会に続き、夜間小集会・
「研究者×博物館×アーティスト 小規模特別展の可能性
~きしわだ自然資料館特別展「モササウルス」の事例より~」
を行います。私も特別展「モササウルス」関係者として
参加、お話する予定です。
同じ時間ある他の夜間小集会も面白そうで、
そっちに参加出来ないのが残念だったり。
●その特別展「モササウルス」の会期は1月30日まで。
1月9日と23日には「モササウルス研究会」を行います。
どちらも私が講師の一人として参加します。
こちらも是非宜しくお願い致します。
特別展「モササウルス」公式ツイッターも宜しく。
・・・・・・・
●恐竜・古生物ブログ「Extinct Creatures」更新。
今回はヘリコプリオンです。
イラストはヤマモトさん、文章は私です。
・・・・・・・
アクロカントサウルス、年内に造形は終わらせて、
年明けに塗装開始と思ってたんですが、ちょっと無理かな~。
2010年12月25日 / その他
12月21日。
この日は毎回お世話になっている京都大学・
近畿古脊椎動物学ゼミの今年最後の発表&忘年会。
本来ならこれに参加するのが礼儀というものなのですが、、、、
日本酒とスッポンと魚に釣られ疋田努先生の
京都大学・動物系統学研究室の忘年会へ!
疋田研の飲み会と言えば日本酒。
アルコールは弱くて、普段は日本酒は全く飲まない
私ですが、この集まりで出される日本酒は大丈夫。
美味しいし悪酔いもしない。といっても、トータルで
紙コップ2杯くらいが限度ですが。また皆さんの
日本酒談義も楽しいのです。
スッポン!疋田先生が捌きました。美味い!

魚!これがまた美味い!
で、そんな御馳走を頂きながら現生動物や古生物の
話をいろいろと伺い、頭もお腹も一杯に。
といっても、やっぱり自分のメインの古生物をおろそかに
してはイケません。という事で、疋田研の忘年会を
少し早目に切り上げ、いつも古脊椎動物学ゼミの懇親会で
使う居酒屋さんに行ってみると、皆さん居られました。
お世話になっている松岡廣繁先生他、学生さん方にも
一年のお礼を言う事が出来て良かった。
オマケ
とうぜんでしょー。
2010年12月24日 / 恐竜・古生物
12月19日
午前中は特別展監修の小西卓哉さんによる展示解説会。
前日のモササウルス化石寄贈の報道の効果もあってか、大勢の方が会場に来られ、中には熱心に質問する中学生も。それも良い質問連発で、小西さん他、私や他の大人達も驚かされました。また、会場には疋田努さんが!事前に知らされていなかったのでビックリ。日本の現生トカゲ研究の第一人者と、トカゲの仲間のモササウルスを海外で研究する小西さんの現生&化石トカゲ(?)研究者2ショットがまさか岸和田で見られるとは! ちょっと感動しすぎてお二人が一緒の画像撮り忘れちまった、、、、(泣)。
午後は前日の古生物復元セミナーに続き、19日はより一般向けの講演「モササウルスのいた海」を開催。
その様子はこちらを。
沼田町化石館の篠原さんの講演では、私が手がけた復元模型(これはまたいずれ改めて紹介したいと思います)の画像も織り込んでの内容で嬉しかったり。沼田町化石館は、大型首長竜の全身骨格を始め、今回の特別展で展示されているモササウルスの1種クリダステス等、多くの絶滅海棲動物の骨格が展示されており、またいつでも挑戦出来る化石発掘体験コーナーも人気。加えて、道を挟んですぐ側には露天風呂付きホテルに、夏場はホタルも観られると、観光と化石が一度に楽しめる場所でもあります。私も二度伺っていますが、篠原さんの講演を聞いていて懐かしくなりました。また行きたいなぁ。
次の小西卓哉さんの講演は、前日とは全く違う内容で、また一般向けという事を考慮しつつも、最新の研究を盛り込んだ内容。小西さんのお話を聞いたら必ず魅了されてしまうその美声と、子供も大人も笑えるユーモアであっというまの講演。
最後は小田隆さんによるプラテカルプス復元画制作の講演。こちらも前日よりも幅の広い参加者層を考慮した構成。下書きから完成へ向かっていく過程には、工程の画像が進む度に子供達が身を乗り出して画面を見入っていたのが印象的。
講演後は、再び特別展会場で小西さんによる解説があり、さらにその後は資料館収蔵庫ツアーへ。
・・・・・
しっかりと良質な素材を集め、その道のまさに最先端にいるエキスパートを集め、それを広報面でもサポートすれば、お世辞にも規模が大きいとは言えない施設で、さらに古生物といえど恐竜のような知名度も無い題材を中心にした特別展と講演でもここまで楽しめる、人も集まる、という事を実感できた2日間でした。逆に小さな施設だからこそ可能だった部分もあったかも知れません。もちろん、それには今迄の資料館の活動の蓄積、特にチリモン関連の活動での資料館の知名度、スタッフの皆さんの経験に負う部分も大きかったように思います。表には出ない資料館スタッフ、友の会の皆さんの理解とバックアップあっての2日間でした。
年明けも、モササウルス展関連の行事は、モササウルス研究会にギャラリートークと引き続き開催されます。残り期間も是非宜しくお願いします。
これだけのネタ仕入れたんですから、当然プラテカルプスの模型、造らないとな!
2010年12月22日 / イベント・教室・講演
12月18日、午前中は各メディアでの報道にもあった通り、きしわだ自然資料館へのモササウルス化石寄贈の記者発表があり、会場には報道関係者が沢山。こういう機会に居合わせられたことは良い経験になりました。
で、午後からは「古生物復元セミナー」
トップバッターは、今回の特別展「モササウルス」監修の
小西卓哉さん(カナダ王立ティレル博物館)。
モササウルスの最新研究の話をがっつり。
小西さんには、毎年SVPでモササウルス情報を伺うのですが、やはり学会中は研究者さんはお忙しいとの事で時間はそれほどゆっくりと取れないのですが、今回は前日の昼食・夕食も御一緒出来て、じっくりとお話出来たのが本当に楽しかったのです。
次は、特別展のメインビジュアル担当の小田隆さん。
3番目は私。マチカネワニ復元模型製作の話をしました。
自分の発表中の画像が無いので、マチカネワニ模型の画像を。
4番目は北川さん(京都大学大学院博士後期課程)のナウマンゾウについての発表。学会や古脊椎動物ゼミでの北川さんの発表を聞いていて非常に分りやすく、話も上手い、それにきしわだ自然資料館にある唯一の古脊椎動物の全身骨格がナウマンゾウという事で講演をお願いしましたが、これがもう見事。あれだけの研究内容を盛り込みつつも、ちゃんと笑いが取れ、しかもこちらの希望通りの趣旨に纏めて下さいました。古生物、特に哺乳類を復元する時には性差によるプロポーションの違いをしっかり把握してほしい、という提言は私達のような仕事をする人間には重要なものでした。
5番目はA.E.Gさんこと藤森さん。趣味として、しかし研究や資料等をしっかりと取り入れた古生復元の楽しみ方をお話して頂いたのですが、、、もーなんていうか、あれほどの話術の持ち主とは!セミナーの発表というより、藤森トークショーといっても良いくらいの会場の沸きっぷり。結果的にセミナーのトリとしての仕事を見事にこなしてくれました。
講演終了後は、特別展会場に移り小西さんその他のよる特別解説。
その様子はこちら。
この日の古生物復元セミナーは、小西さん、小田さんによるモササウルスに関する発表はもちろんですが、きしわだ自然資料館に関係する古生物を題材にした発表、そして私が話を聞きたい人、私が話をしたい事を発表する、という極めて個人的な希望で企画したものでした。また、恐竜のような大物が無くても、地元で見つかっている化石を題材にするだけでも十分面白い集まりが出来るのでは、という意図もあったのです。一方で、こういう企画ではあまり人は集まらないかもしれないな~、という心配もあり、講演者の方には「ほんと少人数の集まりになるかと思うので、、、」なんて弱気な事も言っていましたが、結果的には会場はほぼ定員一杯。資料館に初めて来られた方も結構居られ、嬉しい限りでした。今回のような豪華なメンバーはなかなか難しいですが、今後もこういう集まりが開催出来れば良いな、と思っています。
という事で、次回に続く。